ベアト総受け小説企画ブログです
戦人×ベアトリーチェ
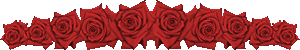
遠くであいつが呼んでいる。きっと現実的な距離感で言えば、遠いよりも近いの方が相応しいその声を、遠くで聞いている。
その声に耳を傾けないように、必死で心を閉ざしていた。
そう簡単には奇跡なんて起きない。
だから、頼むから、邪魔しないでくれ。(ごめん)お前のその声は、思考のノイズでしかない。
ようやく描き終えた毒々しい魔法陣に不備が無いか、最終確認を済ませる。どうやら問題無いようだった。
だから、静かに目を閉じる。
これが魔法だと言うのなら、どうかこの残酷な世界を忘れられますように。
目前に幻視した扉を開く。
ゆっくりと。死んだように冷たいノブを回して。
ベアトリーチェは一人廊下に立ち、舒に深く息を吐く。部屋には確かに気配がしていた。――――対戦相手の。
鍵がかかっているかどうかは大問題だ。戦人が自分をどこまで拒絶しているかの秤である。
現実的に考えれば九分九厘開かない。黄金郷の扉よりは易いか―――否、彼の対魔法抵抗力を思えば凌いだとしても可笑しくはない。
頼む。
許せとは言わないから、言ってはいけないから、千手先を見据えた手をうつのに今すぐにも見返りを求めるのはただの女心なのだから。
「入っていいぜ?」
いつから気付いていたのか、そう不機嫌そうでもない声を受けて厳かに開く。……開いた。
「失礼、する」
少し拍子抜けして、喜びより狼狽と緊張が先にたつ。声も動きも固くぎこちない。
らしくもなく畏まった振る舞いをみせるベアトリーチェに、戦人は思わず小さく笑う。そんなにうろたえなくたって良いのに。
「な、何だよぅ。やけに機嫌良いじゃねぇかよぅ」
「あーわりい」
そう言いつつも、どうしても表情筋は笑みを作り出していた。
ベアトリーチェは思わず面食らい、頭にハテナマークを浮かばせたまま口を尖らせる。
「昨日は怒っていたくせに」
「そういやそうだったな。俺、お前にタンカ切ってたっけ」
「そ、そういやってそなた……絶対に許さないとまで言ったではないか」
この空間で数えれば昨日という日。戦人は至上の遊戯を愉しむベアトリーチェに言い放った。
――――快楽目的で死者を弄ぶことを許さない、と。
その意志はきっと今だって変わっていなくて、自分がそんな風に人を殺せるということを執拗に見せ続ける限り、これからも同じような態度を取る。
――――そのはずだった。
「あー昨日は悪かった、言い過ぎた。とりあえず休戦しよう」
「……酒でも煽ったか? それとも風邪でもひいたか……いや、無能はひかぬか」
「それを言うなら馬鹿な」
無能は否定しないのか。
気にした様子もなくカラカラと笑う戦人に、ベアトリーチェは更に首を擡げる。おかしい。ベアトリーチェは、狂人を見るかのように戦人を見る。
「そんなことより、チェスでもしないか? いやチェスだと気分転換にならねぇか、なら」
「すまぬが、妾は今からロノウェと出かける。どちらにせよゲームは中断だ」
「ロノウェと……お前がぁ?」
同じ場所に長くいればそれは拷問と変わらない。
だから、ロノウェとベアトリーチェの個々が出掛けること自体はそれほど不思議は無い。が、帯同するという部分にだけ戦人は反応する。
「うむ。魔界のアイスクリーム屋がカップル限定のキャンペーンをやっているのだ」
「……へぇ」
なるほど。良い度胸だなロノウェ、後で見てろ。
そう低く呟いた後、困惑するベアトリーチェをよそに口端を上げる。
「ワルギリア、いるか?」
「はい、いますよ」
金色の蝶と共に有限の魔女が顕現する。
「今日暇か?」
「ええ、暇ですが」
「よし、じゃあアイス食いに行かないか?」
「はぁ……良いですが……その……」
ワルギリアは気遣わしげにベアトリーチェに目をやる。
ベアトリーチェがあんぐりと口を開け、咄嗟に反対意見を出すのが遅れている内に言葉が継がれた。
「ロノウェと、な」
「「はぁ?」」
新旧ベアトリーチェは口を揃える。
「ベアトは俺となー」
「待て、え? え?」
逃がさないようにがっしりと腕を掴まれたベアトリーチェは、精神的な意味でも身動きが取れないでいた。
小学生が手を繋いで歩くように腕をぶんぶんと振られ、テーブルの角にぶつかる。たいした痛みもなかったが条件反射で顔を顰ると、戦人は慌てて「悪い」と謝る。
ワルギリアは両者の顔を交互に見詰めながら、もしかしたらと思い付いた可能性を悟られぬよう振る舞った。
「それなら良いですよ。ええ、戦人君が変なことしないようにロノウェと見張ってますからねぇ?」
「なんでそうなるんだよ。アイス食うだけだろ? なぁベアト」
「へ!? あ、うむ!」
言い淀んだのは全く別の理由からだ。しかし訝しんだ戦人は。
「あ。もしかしてロノウェと別のことする予定だったのか? なら俺にもしてもらおうかなァ? いっひっひ」
「何の話だか全く解らぬのだが!」
「ん、冗談を真に受けるなんてお前らしくないぜ。どうした?」
「………」
――――お前らしくない?
まさか今の戦人に言われるとは思わなかった。
確かにこの手の話題を高笑いで返せなかったのは失敗だが、それも彼の変化に比べれば何のことはないだろうに。
そこまで考えて、もしかしたら珍しく大人しい自分に返答しやすい話題を与えてくれたのではと思い至った。だとすれば、いつの間にそんな気遣いを出来るようになったのだろう。
「やっぱり本当に」
「バ・ト・ラ・く・ん?」
「ハイスミマセンワルギリア様」
師匠のフライングな開眼に片言で反省を口にする。尤も、片言すぎて心がこもっているかは定かではない。やっぱり違うかも、と胸中苦笑した。
「ベアト。気をつけた方が良いかもしれません」
「何にだ?」
ワルギリアがベアトリーチェに耳打ちする。戦人には聞かれぬようこっそりと。
「太陽と北風作戦が、気付かれているかもしれません」
途端に、ベアトリーチェの表情が険しくなった。
碧く陰る氷塊を宿した瞳に射抜かれ、ワルギリアは一瞬ぞくりと小さく身体を震わせた。
「――――つまり、妾達の作戦を戦人の側もするつもりでいると?」
「……そう、考えるのが自然です。……この様子を見ると」
ベアトリーチェは無言で頷く。一度ならず幾度も、自分を納得させるように。
――――そう、納得する素振りに見えるのだ。
仮にワルギリアがベアトリーチェのことをよく知らない者だったなら。
「そう気を落とさないで下さい。気付かれているのは誤算ですが、あの露骨な演技のお陰で把握しているという意味では平等です。あとはこちらのゲームメイクで何とかなります」
「むぅ……」
「――――つまり、今日は彼と一時の平穏を楽しみなさい、ということです。それが例えかりそめのものでも、貴女が千年切望した一日には違いないでしょう」
「……。……そうであるな。うむ。くっくっく、戦人め、今のうちに驕っておるがよいわ」
いつもの調子を取り戻したように、嗤う。半分は紛うことなき本心。さりとてもう半分は虚飾だ。
男の優しさが偽りだったことに失望しているわけではない。―――偽りだなんて思っていなかった。
いかな師匠たる魔女に忠告されようとも、彼にそんな器用さがあるとは到底思えなかったからだ。
それだけではない、朧げな記憶を掘り起こして密かに期待していた。
空間。掴み取った無心。魔法陣。
ああ覚えている。忘れていれば良かった。
魔女という身分も忘れ神に近しい者に祈った、その祈りを。
(戦人が自分という魔女を認めてくれて、それどころか全ての真相を理解してくれて。殺し合う必要も憎しみを一身に受ける必要もなくて約束だって思い出してくれて――――欲を言うなら、自分の抱えるものと同じ類の好意を抱いて欲しい)
そんな世界を。何度ベットに横になって目を瞑っても見られないような夢を。
ここにあるのは果たして現?
ここが強欲に貪った夢幻のぬるま湯なら、それにたゆたうのも悪くはない。
(きっと、)
「……」
ベアトリーチェは黙考していた。
この一手を誤ればクイーンは奪われる。ただただ相手のチェックを待つのみとなる。だから、慎重に選ばなくてはいけない。
「……」
「なぁ」
「…………」
「ベアトー」
声をかける戦人を軽く睨む。どうやら彼はもう決断したらしい。
「……なんだ」
「まだか?」
「煩い! 話しかけるな! 集中出来ぬではないか!」
「集中ってよぉ……」
戦人は手元のファイルを持ち上げる。テーブルに乗っているのはチェス盤でも駒でもなく
「季節限定緑茶アイスにするか、お気に入りの紅茶アイスにするか、だろ? そのくらいは や く 決 め よ う ぜ !?」
メニュー表である。
せかす戦人を再び睨んだ。
どうやら辟易しているわけではなく単純に飽きているようだ。同時に、無言で悩んでいるベアトリーチェに無視されているように感じているらしい。全く、たった30分も待てないのか。
前日放置プレイを受けていたベアトリーチェは逆の立場になって優越感を感じる。
「煩い奴だなァ。せっかちな奴はモテないぜェ?」
「お前がちゃんと会話してくれるならあと15分は待ってやるんだがな」
喋って欲しいと。
口も利ききたくないと宣った、その口から。
間違いなくここは我が理想郷なのだ。ベアトリーチェは確信する。
「だから会話してたら集中して決められないではないか」
「会話してなくても同じじゃねーか」
「選べないのだ、どっちも食べたいのだ!」
駄々をこねるベアトリーチェに、戦人は首を擡げる。
「それなら両方頼めばいいだろ?」
「一個にしないと夕飯抜きだとお師匠様に言われた。復唱要求までされた」
「…………そ、そうか」
それで要求を飲んでしまったのか、と戦人は有限の魔女の偉大さを思い知ったのだった。
「よし!」
「お、決まったか?」
「いや」
「え!?」
「最終奥義を使う時が来たようだな、くくく!」
ベアトリーチェがおもむろに取り出したのは銀色のコイン。片面には桜の紋様が、その裏には100という文字が刻まれている。俗世間的なそれはベアトリーチェにはあまり似合っていなかった。
「ただの100円玉じゃねぇか……?」
せめて黄金の魔女らしく純金のコインにしないか? と戦人が呆れ返っていると、ベアトリーチェは「発行されたばかりでぴかぴかなのだ!」と胸を張った。
「うむ、そうであるな。だが妾の手にかかれば『ただの硬貨』では無くなるのだ」
にやりと嗤う彼女を見て、戦人は意味するところを悟る。
つまるところ裏表で決める、運任せな決断をするというだけだ。これも小さな魔法だろうか……リスクが無いからどう言う可きかわからないが。
戦人の想像通りベアトリーチェは表なら裏ならと組み合わせを述べた。
ぱちんとコインを弾き飛ばす。それは綺麗に放物線を描いてテーブルの真ん中に落ちる。
「……見事だな」
「うむ……」
確かに見事だった。
何と言うことだろう、硬貨はどちらの面を上にもせず垂直に立ってしまったのだ。
「ワンモアチャンス!」
ベアトリーチェはめげずに再度弾き上げる。
ぱちん。
再びくるくるとコインは回転し、周りの客が迷惑そうに睨むのも気にせず音を起てて……立つ。
何度やっても、ベルンカステルもラムダデルタも真っ青になるほどに無駄な奇跡が起き続けた。
永続してやっていると次第に客も集まってきて、ロノウェとワルギリアが生暖かく見守っていたりして、もはや見世物だ。この上なく地味ではあるが。
「無限にやる気か?」
「妾は無限の魔女であるからな」
言っている本人も何かが違う、と思ってはいたが、敢えて訂正はしなかった。
「わかった、こうしよう。俺がお前の頼まないほうを注文する。それぞれを半分に割って入れ替えて、形状だけ元に戻す。これで両方食べながらも一個と定義できる。どうだ?」
「は……半分こ?」
ベアトリーチェはついと顔を上げる。
「いやか?」
「い、いやなどではない……ただその……」
「? それなら注文するぞ?」
「うむ……」
すぐに店員を呼びとめ、ベアトリーチェの希望通りに注文する。店員が微妙な顔をしていたのが気になったが、考えないことにして待つ。
どん!
擬音ではなく擬態である。それは、存在するだけでそんな文字が見えるくらいには強烈だった。
「何だこのデカさは!!」
「……カップル用の特大サイズなのだ。これなら赤通り一個でたくさん食べれるのでな」
運ばれてきたのは、直径30あまりのアイスクリーム。それが、二つ。
「俺に食わせる気が無かった所までは把握したぜ」
「ベアト……。やけに素直に赤で応じると思ったらこういうわけですか……」
「ぷっくく」
ふと斜め左の席を見ると開眼している鯖の魔女がいた。笑ってないで宥めてくれよ、ロノウェ。
「ち、失敗したぜ……」
戦人は露骨に舌打ちする。
「何だよぅ、食べれねェなら妾が貰って……やれねェんだったな、うん」
「こんなどうでも良いことでロジックエラーは避けたいぜ。大丈夫、俺は食べれるぜ? むしろお前は」
「そなたはどう思う?」
「うーん。紅茶とアイスは別腹だからな、ベアトは」
「うむ」
戦人はまだ不満そうに、人差し指と親指でスプーンを弄る。
「それに、俺が言ったのはそうじゃねーよ」
「では何なのだ」
てっきりそうだと思いこんでいたベアトリーチェは、興味深げに食いつく。
戦人はひとしきりどもった後、ベアトリーチェの目を見詰める。
「……食べてる間もお前、喋らねぇだろ」
「うむ、お師匠達がエチケットに煩いからなぁ」
普段の傍若無人振りからしたら白々しい理由だ。
こうまじまじと観察しているところからして、真意を悟っていて惚けているのだろう。
「あーもう……皆まで言わせんな。わかってるくせしてよ?」
「くっくっく。コアクマケイとやらは嫌いか?」
「色々考えてるくせに目標達成する前にあっさりネタばらししちまう、アホの子な魔女様なら好きだぜ?」
「む、あほの子とは失礼な……ほぇ!?」
「さーて分けるか。本当にデカイなー」
戦人はアイスをスプーンで等分割し始める。
スプーンが小さいから分けにくい。それ以前にこれ、形保ったまま向こうの皿に移せるだろうか。
「ま、待て今なんと言った!? 聞き逃さぬぞ!?」
(確か確か、妾のことをす、好、)
「さあな、俺は過去の事はいちいち覚えてない主義なんだぜー」
「わ、悪い意味で説得力があるな、そなたが言うと!」
「…………いっひっひ、悪い悪い。おい、アイス溶けちまうぜ」
「あー、妾のアイス! 早く食べぬと、『アイスに対する無限の魔法禁止令』が出てるから戻せねぇんだよ!」
「ワルギリアによる子供のしつけし直し中ってことか」
「むきー! そなたに言われたくないぞ!」
出歯亀が可能な位置を陣取り、ロノウェとワルギリアはお嬢様と対戦相手の愉快な応酬を愉しんでいた。勿論彼らは普通サイズのアイスである。
「ぷっくく。どういった心境の変化か把握は出来ませんが、随分と仲のお宜しいようで」
ワルギリアも同感だった。ベアトリーチェにはああ忠告したものの、静観するうちに自信はなくなっていた。か細い眼を更に細くして、疑わしげにロノウェを見る。
「貴方がクッキーに何か仕込んだのではないでしょうね?」
「とんでもない。仕込むならもっと楽しいものを入れますよ、ぷくく。てっきり何かの戦略かと思いましたが、あの様子ではどうやら違うようでございますね」
「貴方もそう感じるならそうでしょうね」
もしも戦人がロノウェをも欺けるような人間だったら、こちらは即刻リザインすべきだ。
人間である以上万が一にも有り得ないだろう……が。
純粋に気が変わったということだろうか。
――――あんなにも頑なだった彼が?
ベアトリーチェの幸福を誰よりも願う者として、どんなに見せつけられても疑心を拭ってはいけないという使命感があった。
「さて、お嬢様達はまだスウィーツと格闘中でございますが、私共はおいとました方が宜しいのではありませんか? 過ぎた出歯亀を近頃は『KY』と呼ぶそうでございますから」
「近頃の話はわかりませんが、そうですね。あとは若いお二人で、と。ふふふ」
とはいえ―――だからこそ、彼女の幸を祈る者だからこそ、ベアトリーチェの「今」を護ってもやりたい。
ワルギリアは空の食器を置いたまま、伝票を持って受け付けに向かうロノウェを追った。
「それではマダム、せっかくですから私達もこれから二人で」
「申し訳ございませんが、今からガァプとマリア卿が『さくたろの将来を
ワルギリアは間髪を入れずに、且つ心の底から申し訳なさそうに言った。
「ぷっくっく…………………ぷっくっく」
乾いた風の吹く中、どこか虚しい笑声が閉じかけた自動ドアの前で谺していた。
『食事中に話しては"はしたない"』などとはどこの家庭でも幼い頃は教えられるもので、だからと言って黙々と食べ物を口に運ぶ食卓はけして多くない。
何を言いたいのかと言えば、やはりと言う可きかベアトリーチェのエチケット発言は自分の反応を見る為であって、本人にその気は全くなかったようだ。
大好きなアイスを頬張り、もぐもぐと口を動かしながら機嫌良さそうに喋る。アイス効果絶大だ。小動物のような愛らしい仕種の上に会話も大分毒気が抜けている。自分は抜けていなくても大歓迎ではあるが。
多少怪しまれてもロノウェと引き離して正解だった。
お嬢様と執事ポジションを確保しておいてこれ以上の役得は断固として許さない。
(そういえばロノウェ達いたな)
口に出したら薔薇と鯖が飛んできそうなことを考え、戦人はようやくベアトリーチェ以外に視界を広げた。
「あれ? いつの間にかロノウェ達帰ったんだな」
彼らが座った筈の席には誰もおらず、店員が皿を片付けていた。
まあ邪魔者は帰ってくれた方が有り難い。用事が出来たから一緒に帰りましょうなどと言われたりしたら、それが一番最悪だ。
尤も彼らのことだ、普通に場を読んでくれたのだろうけれど。感謝感謝。
「用事でも出来たのではないか? あやつらは別に乗り気ではなかったしのぅ」
「だな。しかしこれ、絶対腹壊すよなぁ」
半分を消化したかどうかの巨大アイス。既に溶けている方が多いのは気のせいだから言及してはいけない。
ベアトリーチェの方はまだ三分の一もいっていないようだ。無論男女差もあるのだろうが、ベアトリーチェは好きなものは味わって食べる派らしく舌の上で転がす時間がひどく長かった。
「例え腹を壊したとしても、この至福の時間には代えられぬわ」
アイスに対する異常なまでの執着心は理解出来ないが、その精神は心から賛同した。
「後で死ぬほどツケを払う羽目になっても、な」
「妾は死なぬぞ!」
「いや、文脈で判断を求めるぜ」
「妾は、死なぬぞぉぉおぉぉ」
よく見れば徐々に顔が蒼ざめていっている。うぐぐ、と唸り始めたので確信した。
「さてはお前、無理してるな!?」
「シテナイゾ!? 妾はア○ガニスタンに棲息するアフリカ象に、これを食べ切ってガラスの家を建ててやると約束したのだ!」
「とりあえず落ちつこう、な?」
戦人とベアトリーチェは人々―――否、悪魔達の喧騒の中を歩いていた。
今は正午を二三時間ほど過ぎた、照り返しのせいで一番暑い時間だ。白く塗装されたコンクリートは見栄えは洒落ていたが、生憎気温を上昇させる働きを熟してしまっていた。
しかしながら二人の体感温度は真逆である。太陽に水蒸気の集合体が被るのも苛立たしい。
「食べ過ぎた……」
「だな。さすがにキツイぜ」
「うぅ、寒いぞぅ……」
ベアトリーチェが身体をぶるり震わせる。戦人も寒いのと気持ち悪いのが融合して何とも言えない感覚だ。
一つを二人がかりでも食べ切れるかどうかという量である。
残念なことに「食べ物を残してはいけません」という教えだけはしっかりと染み付いていたせいで、意地になって完食した。
「うぐぅ……」
「ベアト、とりあえずあそこの公園で休もうぜ」
「うむ……」
後ろ頭に弱々しい返事を聞く。かなりまずいな。
のろのろとついてくるベアトに歩調を合わせ、何度も気にしながらも暫く歩いていたが、不意に気配を失い振り返った。
「ちゃんとついてきてるか? ……!」
いない。いない?
戦人は慌てて周囲を見回す。人間には理解しがたい独特のファッションを着こなす人ならざる者達が、脇を通り抜けていく。
ベアトリーチェらしき人影は、見えない。
(――――クソッ!)
なんでもっとよく見ておかなかったんだ。
違う、どうして彼女の手を握っていてやらなかったんだ。
魔界の街ことはベアトリーチェの方がよく知っている筈だし、それほど心配はいらない?
―――なあ、「そうじゃないだろ?」
ほんの数瞬前までは気配があった。だから、それほど離れてはいないはず。否、離れている方がおかしい。
だから、多分、戻りすぎている。
戦人は足を止め、引き返した。――――あ。
「ベアト!!」
「あ………戦人………ぁ。苦しいよぉ……」
ベアトリーチェは街路樹の鉢に両腕を置いて、踞っていた。低く座り込んでいたから最初は視界に入らなかったのだ。
戦人は迷いなくベアトリーチェの元に駆け寄る。
「しっかり見てなくて悪かった」
「? なんでそなたが謝るのだ?」
ベアトリーチェはもったりと首を傾げた。
「ほら、これ飲めよ」
ベアトリーチェを公園のベンチに座らせ、自販機で買った温かい紅茶を渡す。
戦人の上着をきっちり着込んで丸く固まっているので、缶を開けてやることにした。
「む……すまぬ、今は何も口にしたくない」
「返すなって、持ってるだけでも暖かいだろ?」
ベアトリーチェはこくりと頷いて、手を伸ばす。両手に掴んでじぃっと缶を睨んだ末、結局琥珀色の液体を少しだけ、ゆっくりと喉に流し込んだ。
元の紅がかった頬に戻りほっとした戦人は、ベアトリーチェを下から覗き込むようにベンチの脇にしゃがむ。
「いなくなって、怖かったんだぜ」
「むぅ。妾を子供扱いするな」
今の表情、鏡で見たらそんなこと言えなくなるんだろうな、と苦笑する。
「そうじゃない。二度と、逢えなかったらどうしよう、とな」
自分が言えた話ではないが、大袈裟すぎやしないか。そう考えたベアトリーチェの喉が、再びごくりと鳴る。身体が求めていない水分を吸い込んでしまうのは惰性だ。
「ならば束縛なりなんなりすれば良かろう。金蔵の孫なのだからそのくらいなぁ」
「何だ? 逃げる予定でもあるのかよ?」
他の男の名を出されたのが不快だったのか、戦人が静かに尋ねる。
「そなたが追いかけてくれるなら、それも良いかもなぁ」
「冗談じゃないぜ。追いかけるだけで済むと思っているところが特にな」
「……怖いのぅ」
二人が屋敷に帰る頃には、陽も朱く暮れかけていた。
喫茶室に入るやいなや、ベアトリーチェは勢いよく柔らかいソファに身を投げた。うーんと背伸びすると二人分の荷物を置いた戦人が苦笑する。
「さて、次は何するかな」
「えー、妾疲れたぞぅ」
「んじゃ、本でも読むか」
まあそれくらいならば良いか。そういえば、昔はよくこうやって推理小説を読んで語り合ったりしたな。
そんな風に回想して、書庫から適当に見繕ってきた本を開き始めた。実はとっくに読み終えている本だ。
「うわ、本当にミステリーばかりだな。あ、俺これ読んだことねぇ」
戦人は、無作為にかき集めてきた本のあらすじを漁る。
「そりゃあ、古今東西の推理小説を収集しておるからな」
あまりに屈託なく言うので、戦人はつい「そうか」と受け流した。
こんなの、「魔法は全てトリックで説明出来ます」って言っているようなものだよなぁ。こんなにすぐ近くに置かれたヒントすら自分は見逃してたというのか。
(本当に、俺はベアトを理解しようとなんかしていなかったんだな)
思わず自嘲する。ベアトリーチェの正面に腰掛け、二人を別かつ小さな円卓に据えられた―――今度は間違いなく―――慣れ親しんだ白と黒の盤を見詰めた。
「何をしておる?」
「ん? チェス盤に駒を並べているだけだぜ」
「………」
ベアトリーチェは「読書ではなかったのか」と眉根をひそめる。
確か午前中もチェスがしたいとか言っていた気がする。ゲームで嫌というほと繰り返しているというのに。
(しかし、今なら欝な気分もせぬな)
「いっひっひ、お相手願えますか? 魔女様」
「仕方ないのぅ」
言外に嬉しそうな魔女の態度に、戦人は懐かしむように睫毛を揺らした。
互いにわざと長考する振りをしていた。その分長く時間を共有出来るからだ。
不意にベアトリーチェがぽつりと零す。
「今日があまりにも夢みたいで、明日そなたがいなくなってしまうような気がしてならぬ」
もしかしたら、本当に夢なのかもしれない。だとしても頬を抓ったりだとかは怖くて出来るわけがない。
そもそも夢かどうか確かめるなんて、夢であって欲しいときと現実だと心のどこかで分かっているときに決まっているのだ。
醒めて欲しくないのに、自ら棄てるなんて愚かしいことを誰がしよう。
ああそうか自分は信じていないのだな、と自嘲し、反応のない戦人を覗き込む為に顔をあげる。
――――何故。
………そんなにも傷付いたような眼をするのだろう。
もしかしたら自分は、自身の頬ではなく戦人の頬を抓っていたのか?
「……右代宮戦人は明日もお前の側にいるぜ」
慈しむように優しく笑って、戦人がそう言った。
ベアトリーチェはほっと胸を撫で下ろす。
赤き真実。
それで復唱出来るなら嘘ではない。
赤は魔女が語る、違えられない絶対真実なのだから。
「……あれ?」
魔女ガ語ル、真実?
私ハ彼ニ、使イ方ヲ教エタ?
第三の盤が終わって、戦人がもう一度立ち上がってくるようなら、機を見て教えるつもりではいた。
魔女否定の青と、対峙する赤を。
(でも、………でも……)
「……。……ごめん」
戦人は俯き、そう一言呟いた。
きっとベアトリーチェに気付かせたくてわざと使ったのだろう。
(それはもう時間がないことを示していて)
焦りはなく、ただ苦渋と自責だけを露にしていた。
「謝るなよ、謝るな! それではまるで、」
「右代宮戦人はお前から離れはしない。―――俺じゃない、戦人は」
何を言っている?
戦人は、お前だろう。お前以外にいるものか。
冗談を言っているのだと、……それが赤でなければ笑い飛ばしたものを。
「……そなたは?」
「帰るぜ、俺の時間に。お前のいない、第六の盤終了後の喫茶室へ」
「妾がいない……だと? そなたは、一体誰なのだ? 何の為に」
「俺は…………」
戦人は力強くベアトリーチェを抱き寄せる。
ばらばらと駒達が飛び散る。
「黄金にして無限の魔術師。―――それ以上は、言えない」
黄金、無限。それは、他でもないベアトリーチェが冠する二つ名だ。黄金は碑文さえ解けば譲り渡す。しかし、その程度で無限の名まで譲るわけがない。相手が戦人なら尚更に。
つまり、戦人は知ったのだ。深淵の地底から山頂まで上り詰める術を。
「お前がその言葉を聞きたい相手は、俺じゃない。そこまで分かってて、逢いに来たから」
継いだ言葉は耳を通り抜け、ただ無情な赤だけを反芻していた。
それだけで、ゆっくりと―――そして急激に「戦人」の真実が滲み入る。
(ああそうか。こやつの世界の妾は、消滅という名の岸に上がることを選んだのか)
驚きなどしなかった。いつだって、そうしてしまえば良いと耳元で囁かれ続けている。そう、今ですら。
戦人は俯いて表情を歪ませる。こいつのことだからまた泣いているとばかり思っていたのに、戦人は蚩っていた。
彼はもう泣けないのだ、とベアトリーチェは胸を氷の糸で締め付けられる。
「不毛だなぁ」
ざわざわと竹の葉が擦れるような声だった。
「『死ぬ気でやれ無能』って『俺』に言っておきたかったのに、身体乗っ取ってたら出来ねぇじゃねぇか」
「妾が伝えてやる」
戦人は腕を解くと物哀しげに頬を緩ませ、緩慢な仕草で愛しい魔女の頭を撫でる。
「いや、遠慮しとく。お前が土を被り続ける度、情けなくなるぜ。『俺』には書き置きでも遺しておいてやるさ。お前の悪戯じゃないって言い訳考えとけよ?」
と悪戯っぽく片目を瞑る。つられて、ベアトリーチェも不自然に微笑んだ。
「そなたが何をしようと妾が戦人を追い詰める、それは変わらぬ」
そんな言い訳をしたところで、例えそれを現時点の戦人が信じたところでこの第三の盤の終わる頃には全て嘘になるのだ。
意味がない。意味がない、どうせ。
「――――ベアト」
名を呼ぶのを合図に、それまでの躊躇うような、ごまかすような態度を改め真摯に声音を変えた。
「『俺』は、煉獄山の頂上へ絶対に辿り着く。だから、辿り着けると信じて、『この世界』で待っていて欲しい」
本当に伝えたかったのは、他でもない自分が辿り着いたということだった。そしてそのとき、自分がベアトリーチェに何を想ったのか。―――それをどうしても伝えたかった。
でも、この時間を生きるベアトリーチェには、それはあまりにも……。
「残酷なことを言ってるとは分かってるんだ、でも」
「そなたと約束など、誰がするか」
「約束じゃない。ただのみっともない懇願だぜ」
「……そうか」
ベアトリーチェがほんの少しだけ解放されたように微笑んだ。
ここで「約束」なんて、余計に彼女を泣かせることにしかならない。反古にするなど「自分」が許さないけれど、彼女の刻々と迫る時間をそんなものの為に費やして縮めさせるものか。絶対に、繰り返させるものか。
「俺は、何度お前を傷つけたら気が済むのだろうな」
「三番目の傷つけ方はそなたの専売特急であるわ」
本当に、その通りだ。
後悔してもしきれない。
「本当は、お前に会いたかっただけなんだよ」
色々なこと、伝えたかったのは本当だ。
だとしてもそれだけなら、1500秒の10分の1もあれば充分余りあるのだ。
それだけで満足出来なかったからこそ、こうやって留まって"ままごと"を熟していた。
結果的に、互いが深く傷つくことになるのは、目に見えていたのに、だ。
それでも、どうしても逢いたかった。
(彼女を振り切ってでも)
これがエゴでなければ何だと言うのだろう。
「……目を閉じてくれ」
これ以上、長引かせるのは"ひび"を広げることにしかならない。
――――結局、自分の自己満足だったな。
今更土で塗り固めてもいびつで軟弱になっているかもしれない。
「て」
ベアトリーチェが一文字だけ呟く。
「手?」
「そう、手」
戦人は言われるがままに、ベアトリーチェの右手を取る。
「続けて良い」
「………さあさ思い出してごらんなさい、俺達の本当の世界はどんな世界だったか?」
「次に目を開いたら、そなたは妾を憎いと言うのだな」
「……」
「それでも。……きっと約束は、果たされるよな」
今度こそ。
敢えて「約束」という単語を使ったベアトリーチェの意を汲み、戦人ははっきりと頷く。
例え瞑ったベアトリーチェの眼差しが捉えてなくとも、しっかり伝わったと確信した。
「召喚に応えてくれたことを感謝する。どうやらお互い様だったようだがのぅ」
「ベアト」
戦人は空いた右手でベアトリーチェの赤褐色の視界に蓋をして、昏くぼんやりとした精神を繋ぎとめていた理性から解放する。
「おやすみ」
というただその一言で。
もしも、そう。
これが泡沫の夢だったとしても。
(その瞬間が本当に幸せだったのなら、どんな代償も支払うと決めました)
ベアト。ベアト。
呼んでいるのは、どこまでも聞き慣れた声。
その声の主に思いきりしがみつきたい気も、振り切って夢の中に沈み留まっていたい気もした。
「起きたか?」
右手に感じる硬い温もり。無骨な男の手が、絡ませるでなくただ自由にさせるように手元に置かれていた。
羊水から抱き上げられたかのように急速に目が冴えて、産声を上げざるを得なくなる。
そこに彼が"い"たからだ。
「……。……ばとら!?」
「……手。離せ」
戦人はぶっきらぼうにそれだけ言う。
その声調で完全に目がさめた。
(いつもの、戦人だ)
「振り払えばよかろう」
声が震えるのを堪える。
「その顔で言われても困るんだがな」
「え? ……あ」
水晶のように煌めくそれを、自覚するまでに数秒を要する。
「そ、そなたが手を握ってたから拭えなかったのだ」
「知らねぇよ」
現に今、空の左手で拭っている。八つ当たりも良いところだだ。―――拭えなかったことに関しては。
「………」
戦人は黙り込んでいた。快く思っているわけもないだろうが自分から離そうとはしない。相変わらず甘い奴だ。
その甘さに思わず笑みが零れてきて、結局書き置きを忘れた同じく詰めの甘い彼の代弁をしてやることにした。
「『そなた』からの伝言である。『死ぬ気でやれ無能』」
「……………。黙れ」
戦人は下唇を噛む。今、一番言われたくなかった事を言われたのだ。
「妾は伝えただけであるぞォ?」
「それ以上言うな」
ベアトリーチェが手を離す。戦人は黒瞳の動きだけで魔女の指先を追うと、ややあって苦しげに
「お前が言わなくても、聞こえてたんだよ」
そう一人ごとでありつつ相手に伝えたくて仕方ない、不器用な声量で言った。
(―――聞こえてた?)
ベアトリーチェは瞠目した。確か、乗っ取っているから言えないとか宣ってはいなかっただろうか。
『書き置きでも遺しておいてやるさ』
まさか、忘れていったのではなく、ちゃんと書き込んでいったというのか?
この戦人の、記憶に。
どうやらその推理は正解のようで、戦人は他に何も覚えていない。
ああ、そうか。
これも太陽なのだ。あの彼も分かっていてやった筈だ。
――――太陽なのだ。北風よりも戦人を揺さ振るものとして意図せずともどうせ利用している。今も、―――否、今現在の自分の感情が通り雨のように流れ去った100分の1秒先から。
それでも。何かが変わるような気がして。
その為に、「あいつ」が来たような気がして。
また期待する自分が、沸き上がり始めた。
「それで? どうしたんですか?」
六番目のゲーム盤に蓋をして、戦人ともう一人、彼が蘇らせた新しいベアトリーチェが二人だけで茶会を開いていた。
「どうって言われてもなぁ……。二分の一の、すれ違わない世界になればいいな、としか」
潮は引かなければ満ちない。
もしも彼らが「満ち潮」を掴み取れたなら、ベアトリーチェを失った魔術師など存在しないのだから、次の巡り会わせは「引き潮」だ。
満ち続けることは有り得ない。
まあ親殺しのパラドックスというやつだ。
しかし、過去の親を殺しても現在の親は死なないがもしも平行世界―――否、列車のように世界が組み立てられているのなら、自分のいる世界とは別に自分も親もいない全く違う世界が後ろにあることになる。
「そうですね」
「あとはロノウェをシメてくる。役得とか許せねぇ」
「くすくす、そんなに良い思いしてきたんですか? 羨ましいです」
「……お前も会いたかったか? あいつに」
可愛らしく嫌みを口にされ、戦人後ろめたい気持ちになる。
「当然です。それなのにお父様は私に黙って儀式を成功させてしまって」
「ごめんな。失敗したら時空の狭間に閉じ込められかねない、危険な賭けだったんだ」
「わかってます、私が付いて行けるほどの奇跡の余裕がなかったことも。それでも私はお父様の娘であり、お母様の娘ですもの」
「いっひひ、それだけ聞くとどこまでも当たり前のことだなぁ」
「確かにお母様からお父様への恋心は譲られましたし、駒の私達は結ばれました」
蓋を閉じた、第六の盤を優しく撫でる。
戦人が、ベアトリーチェの望みを叶える為に紡いだゲーム盤。黄金郷という名の箱庭で三組の恋人達は結ばれ、永遠の愛を誓いあった。
その中に突っ込まれた「戦人」と「ベアトリーチェ」の駒。
久遠に戻らぬかつての彼女の望みを叶える為に。
行き場のない彼の想いを注ぎ込む為に。
人形遊びと言ってしまえばそれまでだが、並べられた二つの陰は確かに慰めだけを与えてくれた。戦人と、母を失った新しいベアトリーチェに。
「でも、『私』はお父様の娘なのです。恋慕の情ではなく、生み出し慈しんでくれた者への愛なのですから」
母の叶わぬ恋情を叶える為に生み出された娘。
けれど娘が男に抱いたのは父親に抱くそれで、男のそれも恋心には成り得なかった。
「俺とあいつの子にしちゃ、出来過ぎだな。お前は」
「そうですね」
「……きっぱり言うな」
正直なところ、戦人はまだ完全に彼女を受け入れられたわけではない。
姿形からして娘という歳ではないし、何より母であるあのベアトリーチェに―――「一生分の奇跡」を注ぎ込んでも、一度きりの邂逅を求めた愛しい女性に―――あまりにも似過ぎていた。
今でも、顔を合わせるのが辛くて仕方がないときもある。
それでも、娘として受け入れられるという自覚が、少しずつではあるが確実に流れ込んできているのがわかっていた。
魔女の死を、二人が受け入れるには千年を越える時間がかかるかもしれないけれど。
第十の晩に、旅は終わり、黄金の郷へ至るだろう。
魔女は賢者を讃え、四つの宝を授けるだろう。
一つは、黄金郷の全ての黄金。
一つは、全ての死者の魂を蘇らせ。
一つは、失った愛すらも蘇らせる。
一つは、魔女を永遠に眠りにつかせよう。
安らかに眠れ、我が最愛の魔女ベアトリーチェ。
End
(あとがき? いいえ言い訳です)
この度はこのような素敵な企画に参加させていただき、ありがとうございました!
未だビクビクしながら壁|`)から顔を出しております、ええ。
致命的に遅筆なせいで48日という謎の制作時間をかけたバトベアですが、実は金ベアの話と対になるように組み立てられた、もっと短い話の予定でした。しかも一貫してラブコメの。
どうしてこうなったとか言ったら駄目です(´・ω・`)
どちらも独自解釈が多いので、不快になられた方がいらっしゃいましたら申し訳ありません。
自己満足をもってお送りいたしましたSSを、ご読了頂きありがとうございました。
椎名桜花
PR
